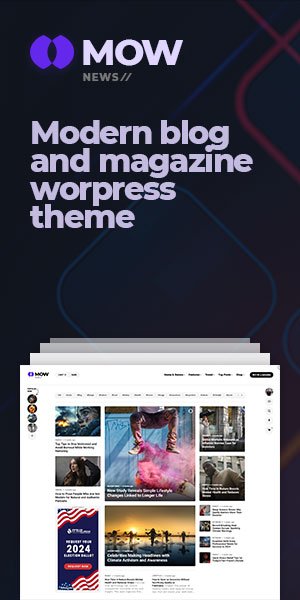Now Reading: ボルダリング初心者の5級攻略!これだけは覚えておきたい7つの基本
-
01
ボルダリング初心者の5級攻略!これだけは覚えておきたい7つの基本
ボルダリング初心者の5級攻略!これだけは覚えておきたい7つの基本


「ボルダリングやってみたけど、5級になると全然できなかった…コツとかあるのかな」
「どうしたら上達できるんだろう? まずは5級が登れるようになりたい」
という人、けっこう多いのではないでしょうか。
多くのボルダリング初心者にとって、「5級」は最初の関門になることが多い難易度。
腕を磨いて攻略したくても、何から手を付けて良いか分からないと途方に暮れてしまいますよね。
そこで、初心者が5級を攻略するためのテクニックを最短・最速で身につける方法をご紹介します。
↓↓この記事を読むと分かること↓↓
- 初心者がステップアップするために必要なこと
- ボルダリングの基本中の基本
- 効率的に上達するジムでの過ごし方
実はボルダリングって、上達のためのステップがはっきりしていないのです。
たとえば水泳のクロールだったら、最初はばた足を覚えますよね。
ばた足を覚えようとする場合、下記のようにステップを踏むと思います。
- 腰掛けばた足
- 壁ばた足
- 顔を水につけてばた足
- ビート板でばた足
こういう分かりやすいステップがあると良いのですが…
残念ながら、ボルダリングについては「メソッド」のようなものがあまり確立されていません。

始めたばかりの人が悩んでしまうのも無理ないですよね。
この記事では、僕が10年以上インストラクターとしてキッズや初心者を見てきた中で、まずはこれだけやればOK!と思うことをまとめました。
初心者がどうしたら最初のハードルを越えられるか、長年をかけて考え試行錯誤してきた結果です。
勇気を持ってボルダリングの最初の一歩を踏み出そうとしている皆さんのために、手助けになれることを願っています。
ぜひ最後まで読んで、そしてすぐに実行してみてください。
なぜ5級なのか
まずは目標設定について、ちょっと立ち止まって考えておきましょう。
グレード(難易度)って結構あやふやなもの
初心者の目標として「5級攻略」を掲げましたが、グレード(難易度)はただの目安です。
そもそも、ボルダリングの「○級」という難易度表記には、確固とした基準があるわけではありません。
ジムによって、あるいはセッター(課題を作る人)によって、「5級ってこれくらい」という感覚に基づいて設定されていることがほとんど。
だからあまり数字にこだわりすぎず、目安程度に考えておけばOKです。
大まかな目安としての5級
とはいえ、グレードの数字がまるっきりアテにならないのでは意味がありませんよね。
大まかな目安としてはちゃんと機能しますのでご安心を。
僕の体感では、少なくとも首都圏内の多くのジムにおいて、8級~5級あたりの難易度にはそこそこ統一感があります。
だいたい一番易しい課題が8級くらいから始まって、6級までは初心者でもセンスが良かったり基礎力のある人ならいきなり完登できる可能性のあるレベル。
そして5級に入ると、「ちょっとボルダリングっぽい動き」を要求されることが多いのです。

これが、5級が最初の関門になる理由ですね。
場合によってはそれが6級であったり4級であったりするかもしれませんが、ひとまずここでは
「初心者がテキトーにやってもまず登れない、でもちょっとしたコツさえ分かれば登れる可能性がある」
というレベルが5級くらい、ということにして話を進めましょう。
まずはたくさん登ること
さて、では初心者が5級を登るために必要なこととは何でしょうか?
ここで身も蓋もない結論をまずひとつ。
細かいことを抜きにすれば、一番簡単で確実な方法があるのです。
それは「とにかくたくさん登る」ということ。
ぜんぜんゴールできなくてもいいし、テクニックも何も分からなくてもいいから、とにかくできるだけ長い時間ホールドにしがみついてさえいればOKです。
1回ボルダリングデビューしたら、できれば2週間以内にもう1度は行きましょう。
2週に1度よりは週1回、週1よりは週2のほうが早く上達します。

なんじゃそりゃ、と思われるかもしれませんが本当です。
ボルダリングは「つかまる力=”保持力”」がなくては何もできません。テクニック以前の問題ですね。
逆に言うと、保持力さえあれば、細かいテクニックを無視してもある程度は登れます。

ただほとんどの場合、初心者にはこの基礎的な保持力がまだないのです。
そして、この力は日常生活や他のスポーツで培われることがほぼありません。
つまり伸びしろがたっぷりとあるわけですね。
その分、初心者ほどやればやるほど保持力がぐんぐん伸びて、前回は難しかった課題がいとも簡単に登れるようになっていきます。
テクニックのことを考えるのは、それからでもいいかなあと個人的には思うのです。
とはいえ、「コツを教えて」と言われて「たくさんジムへ行くといいよ」というのではあんまりですよね。

これで終わるわけではありませんのでご安心ください。
テクニックというほどのことでなくても「これだけでも覚えておくとずいぶん違うよ」ということはちゃんとあります。
今回はその超基礎ともいえるコツについて解説することにしましょう。
ボルダリングの超基礎
まずはざっとご紹介します。
- 着地の練習をしておく
- スタートからゴールまでホールドを確認して、1手目をどちらの手で取るかだけ決めておく
- つま先(足の親指)を使う
- 手を伸ばす前に足を動かす(次の手を離せる体勢に)
- 片足は壁でもOK
- ちょっと届かない…というときは「せーの、ほっ!」で勢いよく手を伸ばす
- 休んでから登る
これだけ。
読めば分かる、言われれば実行できる程度のことでしかありません。
しかし、いきなりこれが全部できる初心者はほとんどいないのです。
上でも述べましたが、基礎的な保持力がつくまでは、これだけ覚えておけば充分。

これでちゃんと5級は登れるはずです。
ひとつずつ解説してきましょう。
1. 着地の練習をしておく
これが大事な理由はもちろん、安全性を確保するため。
同時に、怖くて体が動かないという状態を改善するためでもあります。
高いところが怖い、というのは当たり前で、身を守るために大切な感覚です。
しかし恐怖心ばかりが先に立ってしまうと体が硬直してしまうため、まずは少し高さに慣れると良いでしょう。

そのために、着地の練習が効果的なのです。
最初は膝くらいの高さからはじめましょう。
マットの弾力を感じて、膝のクッションを使って着地する感覚をつかんでください。
徐々に高さを上げていって、最終的にはゴールに手が届くくらいの高さから飛び降りてもきちんと着地できるようになればベストです。
ポイントは、
- 高さを確認してから飛び降りる
- 着地点を見る
- 下に手をつかないこと
- 前屈みにならず、膝を折りながら後ろに転がるようにする
落ちてもちゃんと着地できるから大丈夫、という安心感が生まれると、高いところでも自由に動くことができるようになると思いますよ。
2. 簡単なオブザべをする
当然ですが、行き先が分かっていなければ上手に登ることはできません。
上手な人をよく観察すると、登り始める前に手を動かしながらシミュレーションを行っているのが分かると思います。
これを「オブザベ」と呼んでいます。「Observation」 の略ですね。
ダサいっちゃダサいですが、とにかく慣習的にそう呼んでいるので気にせずオブザベオブザベオブザベと100回唱えましょう。
上手な人のオブザベは、実際に登り始める前に「最初はここをこう取って、足をあっちへやって、こうバランス取って……」と計画を立てているわけです。
しかし初心者にはそこまでできません。
ただし、なるべく迷子になってしまわないように、以下の2つのことだけやりましょう。
- スタートからゴールまで全てのホールドを指さし確認する
- 最初の1手を右手で取るか左手で取るか考えておく

これならできそうだね。

これだけのことで良いのですが、初心者できちんとこれをやる人はかなり少ないですよ。
3. つま先(足の親指)を使う
クライミングシューズは、8割方つま先しか使いません。
それも、つま先の内側(親指側)だけ。
あとは使うことが多い順に
- つま先の外側
- 足の裏の前1/3くらい
- カカト
- 足の甲
も使いますが、圧倒的につま先の内側が多いです。
そして逆に、使わない場所もあります。
それは足の裏の真ん中、土踏まずのところです。

しかし初めてボルダリングをやると、なぜか足のど真ん中でホールドに「ずんっ」と乗ってしまう人が結構少なくないのです。
つま先を使ったほうが良い主な理由は、
ということです。
最初は不安に感じるかもしれませんが、問答無用で覚えておいてください。
初心者は、足の、お や ゆ び を つ か え !

これはマジで超だいじ。
4. 手を伸ばす前に足を動かす
ひたすら手ばかりを上へ動かして体が伸びきってしまう、というのもよくあるパターンです。
手を伸ばしてホールドをつかむ、というイメージが強いせいかもしれません。
当然ながら手だけでは登れないので、足も動かしましょう。

いつ?どれくらい?どっちの足をどこへ動かすの?

って迷いますよね。
そこで…もちろんケースバイケースですが、とりあえず一番ハズれにくい公式をひとつだけ覚えて挑みましょう。
それはこんなのです↓
Success
- 右手を出したいときは右足を(手を出すのと同じ方向へ)動かしてから
- 左手を出したいときは左足を(手を出すのと同じ方向へ)動かしてから
まずはこれだけ覚えておいてください。
もちろん、そうしたくても体が言うことを聞かないときは直感に従って構いません。あくまでも基本ですから、すべてに当てはめることはできません。
右上にある次のホールドを右手で取りたいなら、まずは右足を右上の位置にあるホールドへ動かすことを考えましょう。
ちょうどよさげな位置に足を動かせればべりーぐっど!続いて狙っていたホールドに右手を伸ばしましょう。
よさげな位置にホールドがなかったり、どうしても足が動かせないときもあるでしょう。

そういうときはまあ、とりあえず一旦忘れてOK。
でも初心者向けの課題なら、だいたいこの動きで攻略できるように設計されているはずです。
5. 片足は壁でもOK
初心者は両足をホールドに乗せていなければいけないと考えがちですが、そんなことはありません。
片方の足がホールドに乗っていれば、もう片方の足は宙ぶらりんでも良いのです。
というか、厳密に言えば宙ぶらりんではなく、壁に押し当てておきます。
これはとっっても大事なことで、「スメア(スメアリング)」といいます。

英語で「塗りつける」とか「こすりつける」みたいな意味ですね。
その名の通り、片足を壁にぐっっとこすりつけるようにします。
ところで、
覚えていますか?
そう、おやゆびです。
そうすれば、ホールドがないところでもバランスを取るために足を使えます。
ただし、スメアだけで体を押し上げるのは無理があるので、あくまでもバランスを取るだけ。
軸となる足はホールドをしっかりと踏んでいる必要があります。

軸足ってどっち?
それは、4で解説した「右手を出す前に右足を上げる」のときの右足です。
右手を出すなら右足は必ずホールドに乗せましょう。

でも反対の足は、壁に当てるだけでも大丈夫だよ、ということです。
6. ちょっと届かない…というときは「せーの、ほっ!」で勢いよく手を伸ばす

あと少しで次のホールドに手が届くのに…という場面があると思います。
そういうときは、思い切って飛びつくくらいの勢いでいきましょう。
飛びつくといっても、実際にジャンプまではしなくていいんです。
少し勢いをつけて「パッ」と手を伸ばすだけ。
でも最初は、勇気が出なかったりしてうまくできない人も多いです。
そんなときは「せーの、ほっ!」と口に出して、「ほっ」のところで出してみるといいですよ。

これができると、小柄な人でも登れる課題がぐんと増えます。
7. 休んでから登る
登っていると腕が疲れてきます。
そして疲れ切ると、ホールドにつかまっていられなくなってしまいます。
ゴールする前に疲れ切ってしまえば、脱落せざるを得ないでしょう。

でも、休憩を取れば回復します。
たとえば最初は10あったパワーが、1回のトライ中に3くらいまで減ってしまい、ゴール前に落ちてしまう。
でも5分休めば8までは回復するのでまたトライできる、というようなイメージです。

これを5分待たずに、まだ6までしか回復していない状態でもう1度トライしてもたぶん登れませんよね。

だから焦らずに、1回登るごとに休憩を取りましょう。
休んでいる間は次の課題のオブザベをしたり、友達としゃべったり、スマホでSNS巡回したりゲームやったりしていればいいのです。
ところで、疲れが重なるとだんだん回復が追いつかなくなってきます。
10分休んでも20分休んでも、もう5より上には回復してこない、というふうになったらその日はゲームオーバー、今日のところは退散しましょうとなるわけですね。
その日に運用できる保持力を有効に使うために、トライの間のインターバルをとることはとても大事です。
ただし、純粋なトレーニングとしてならインターバルなしで追い込むのも有効です。
- 課題を完登することを目的としたトライならしっかり休憩を取ってから
- 次回強くなって戻ってくるために自分を追い込むなら休憩を短く
というふうに使い分けられると良いでしょう。
5級攻略の1dayプラン
5級を攻略するということを1つの目標として、どのようにジムで過ごしたら良いでしょうか。
ここではおすすめの1デイプランをご提案します。
といっても別に、まるっきりこの通りにする必要はないですよ。
あくまでもたとえというか、提案です。
1. ウォーミングアップ
筋肉や関節をあたためて、少しテンションを上げるためにアップは大事です。
でも実際に登ってアップしようとするともうそれで腕が疲れてしまうので、違う運動で体をあたためましょう。
ジムまで走って行ってもいいし、動的ストレッチも良いでしょう。
キッズはよく縄跳びを使ったりしています。
迷ったらラジオ体操がおすすめですよ。
どれも嫌だ!というひとは、別に無理にアップしなくてもOKです。
軽めの課題から登り始めれば自然にあたたまりますからね。
2. そのジムで一番易しいレベルの課題を1つか2つ登る
完登はできてもできなくてもいいので、一番下のグレードから2つくらい選んで登りましょう。
オブザベを忘れずに!
ちゃんとスタートからゴールまで指さし確認して、1手目をどっちの手で取るのか決めてから取りかかってくださいね。
降りるときには、着地の練習をかねて、十分に注意しながらちょっと飛び降りてみても良いでしょう。
3. 前回できなかった課題をやってみる
初めて訪れるジムでない場合は、前回トライしたけれど完登できなかった課題があるはずです。
それを今日、まだ疲れていないうちにもう一度やってみましょう。
ただし1トライだけ。
案外、疲れてさえいなければサクッと登れてしまうことも多いものです。
1トライで完登できればとりあえずOK、やっぱり無理だったら一旦呼吸を整えましょう。
4. 呪文を唱える
上で解説したことを心に刻んでください。
「おやゆびをつかう!」
「みぎあしあげてみぎてだす!」
「左足上げて左手出す!」
「片足はカベ、片足はカベ」
「せーの、ほっ!せーの、ほっ!」
できれば声に出して10回ずつ唱えてください。
5. さっきの課題を登る
さきほどのトライで完登できていてもいなくても、上述のことを心に刻んだうえでもう一度登ってみます。
前回よりも易しく感じたら最高。
考え過ぎちゃって逆に上手く動けなかったら、一旦全部忘れて①だけ覚えましょう。
「おやゆびをつかう!」
これだけでも充分です。
6. 5級の課題をやってみる
目標の課題にトライします。
自分にとって強度が高めの課題であるはずなので、1トライごとに時間を計って最低5分間は休憩を取りましょう。
1トライしたら5分休む、を気力を保てる間だけ続けます。
回復が遅くなってきたら休憩時間を長くしましょう。
7. 間を置かずに登りこんでトレーニング
もう今日はグレード更新は無理だ、となったらあとは次回のためにトレーニングといきましょう。
課題は何でもOKですが、迷ったら6級→7級→8級とグレードを下げながら全部の課題を触っていくのがおすすめです。
手に力が入らなくなるくらいまで頑張ったら、次回はさらに強くなって戻ってこれるでしょう。
8. クールダウン&ストレッチ
最後にゆっくりと呼吸を落ち着かせながら、軽めのストレッチをすると良いでしょう。
ただし筋肉が疲労していますので、無理に力をかけて伸ばすような体操はNGです。
心地よく感じる範囲で、体をいたわるようにストレッチをしましょう。
まとめ
大事なポイントを復習します。
- 着地の練習をしておく
- スタートからゴールまでホールドを確認して、1手目をどちらの手で取るかだけ決めておく
- つま先(足の親指)を使う
- 手を伸ばす前に足を動かす(次の手を離せる体勢に)
- 片足は壁でもOK
- ちょっと届かない…というときは「せーの、ほっ!」で勢いよく手を伸ばす
- 休んでから登る
そしてとにかくたくさん登ること、でしたね。
がんばってみてください。Good luck!!
おまけコラム;登れたらうれしい○級
ボルダリングを続けていくと、自分の中に「○級ってこれくらい」という感覚ができてきます。
そのときに自分の感覚にそぐわない課題に出くわすと「こんなの○級じゃない!」と言いたくなるときがあるかもしれません。
でもそれって疲れます。
そもそもグレードって曖昧なものなので、自分が思っているよりも難しすぎたり簡単すぎたりするたびに異議申し立てをしていたらキリがありませんよね。
もしそんな発想から逃れるのが難しく感じたら、おすすめの対処法があります。
それは、グレードの数字の前に「のぼれたらうれしい」をつけること。
そして、数字の後ろに()をつけて「のぼれなかったらそれはそれ」としておきましょう。
登れたら嬉しい6級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい5級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい4級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい3級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい2級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい1級(登れなかったらそれはそれ)
登れたら嬉しい初段(登れなかったらそれはそれ)
ということですね。
グレードは、登れたときに喜ぶためにこそあるものです。
すべてのグレード表にこう書いてあったらいいのになーと思っています。
(セッターにとってはそれじゃダメですけどね。)